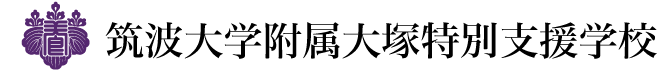学校教育目標・学校運営方針
<令和7年度 学校教育目標>
【目標】
1.知的障害のある幼児児童生徒に対し、幼稚部・小学部・中学部・高等部を設け、教育法規や一人一人の教育的ニーズに基づいた指導・支援を行う。〈根拠に基づいた教育〉
2.知的障害のある幼児児童生徒に対し、自立と社会参加に必要な資質・能力を培うため、適切な指導・支援を行う。〈自立と社会参加に向けた教育〉
【育てたい力】
○人と共に様々な活動に参加する力を身につける。
○主体的に生活に臨む力を身につける。
○社会生活に必要な知識・技能や問題解決する力を身につける。
<令和7年度 学校運営方針>
本校は、変動する現代社会に不断に対応し、多様性や柔軟性のある新しい教育・研究に率先して携わっていく。それを実現するために、筑波大学附属学校群のミッションと3つの拠点構想(先導的教育拠点/国際教育拠点/教師教育拠点)を柱とした学校経営に取り組む。
1. 知的障害教育を担う附属学校として、専門性の充実・発展、教育実践成果の発信に努める。
2.附属学校として社会に貢献できる学校づくりを目指す。
3.大学・教育局・他の附属学校と連携し、大学の附属学校群として、今日的教育課題に対応する。
<筑波大学附属学校群のミッション>
Design Education for Inclusive and Global Society
(インクルーシブでグローバルな社会を実現するための教育をデザインする)
〇時代を切り拓く教育のデザインと革新的な教育実践の追求
〇多様性を尊重しインクルーシブな社会を実現する人材の育成
〇グローバルな視野をもち持続可能な社会を実現する人材の育成
〇パートナーシップによる未来の共創
〇ウェルビーイングの向上と安全安心な環境の創出
<本年度の重点目標>
|
分野 |
重点目標 |
具体的方策 |
|
教育課程・学習指導 |
◯現行学習指導要領に基づき、児童生徒一人一人の実態に応じた授業づくりを推進し、主体的に学ぶ力と社会参加・自立に向けた基礎的な資質・能力を育成する。
◯研究開発学校として、理科・社会・小学部生活科における先進的な実践を行い、知的障害教育の新たな在り方を創造・発信する。 |
◯学習指導要領のねらいと児童生徒の実態を踏まえた単元計画を設定し、学習者の興味・関心に基づいた体験活動や課題解決型学習を取り入れ、主体性を引き出す授業を構築する。 ◯研究開発の最終年次(4年目)として、これまでの研究成果をまとめ、次期学習指導要領改訂に資する資料として「学習指導要領(生活科・理科・社会科)草案」を作成する。また、知的障害特別支援学校における教科別の指導事例として、単元デザインから授業実践を発信する。 |
|
進路指導・ 生徒指導 |
◯カフェ店舗型教育施設「えがおカフェ」などの職業学習の場を活用し、児童生徒の社会的・職業的自立に向けた力を育成する。 ◯自己と他者の存在を尊重し合う意識を育み、いじめの未然防止と早期対応に努めるなど、安心・安全な学校生活の中で豊かな人間関係を築く力を育成する。 |
◯「えがおカフェ」での体験を中心に、段階的な職場・就業体験(校外活動含む)へとつながるようなカリキュラムを整備する。 ◯自己決定・自己表現の場を日常的に保障し、自己理解と他者理解を深める時間を意図的に設定する。いじめ防止については安全委員会(含むいじめ防止対策委員会)を設け、定期的に開催する。また、児童生徒の理解しやすい方法で学校生活に関するアンケートを実施し、実態の把握に努める。また学校評価により取組の状況を客観的に確認し、改善につなげる。 |
|
保健管理・安全管理 |
◯幼児児童生徒一人一人の健康状態を的確に把握し、日常的な健康管理と自己管理能力の育成を図る。
◯危機時の対応力を高め、安心・安全な学校環境づくりを推進する。 |
◯学校安全衛生・保健給食マニュアルに則り、保健指導(スマイル等)を通じて、生活リズムや衛生習慣、感染症予防に関する自己管理意識の向上を図る。 ◯危機管理マニュアルに則り、発達段階に応じた避難訓練を計画的に実施し、防災に対する知識と経験を増やせるようにする。 |
|
組織運営 |
◯11附属学校が共有する今日的課題(インクルーシブ教育・発達特性の理解など)に対し、特別支援学校の視点から提言・支援を行い、共通の解決策を提案する。 ◯ICTツール(Teams、UTOS等)を活用し、校務の効率化と教職員間の情報共有を推進する。 |
◯筑波大学の教育研究機関・教員と連携し、特別支援学校の実践知を活かして、11校共通の課題や授業づくり・支援の方法を共同で検討する。 ◯Teams・UTOS・校内サーバの活用を通して、学校全体でカリキュラム・マネジメントに取り組むとともに、会議(議事次第の集約・議事録の共有等)の円滑な進行及び効率的な情報共有を図る。またこれらを通して、業務内容の可視化や適正な業務分担を推進し、職員一人一人の作業負担の軽減を目指す。 |
|
その他 |
◯地域に開かれたカフェの運営を通して、卒業後の移行支援と社会貢献の在り方を試行・推進する。 ◯企業との連携により、障害のある生徒のキャリア形成を支えるモデル的な取組を創出・発信する。 |
◯学校が主導し、卒業後の就労支援・社会参加のステップとなる機能を持たせた仕組みを試行的に構築する。 ◯本校での実践をモデル化し、今後の特別支援教育と就労支援のあり方について発信していく。 |
<その他>
(1)安心・安全な学校環境
①「大塚教育憲章」「いじめ防止基本方針」「内規」を周知確認し、教育活動その他の全て業務に於いて人権尊重を徹底する。
②安全委員会(いじめ防止対策兼、人権・ハラスメント防止)を中心に、ハラスメントの抑止と早期対応に努める。
③「危機管理マ対応ニュアル」「保健・給食マニュアル」に基づき、幼児児童生徒と教職員の安全と衛生環境を向上させる。
(2)ICTツールの活用と環境整備
①校内分掌のICT教育・情報環境担当を中心にICTツールの環境整備や活用(ミライの体育館を含む)について研修を重ね校内に伝達すると共に、全国へも発信する。
(3)外部機関や地域社会との連携
①えがおカフェ(ガレージ・カフェ)の活動を継続実施し、地域社会に本校の取り組みを紹介していく。